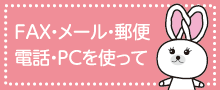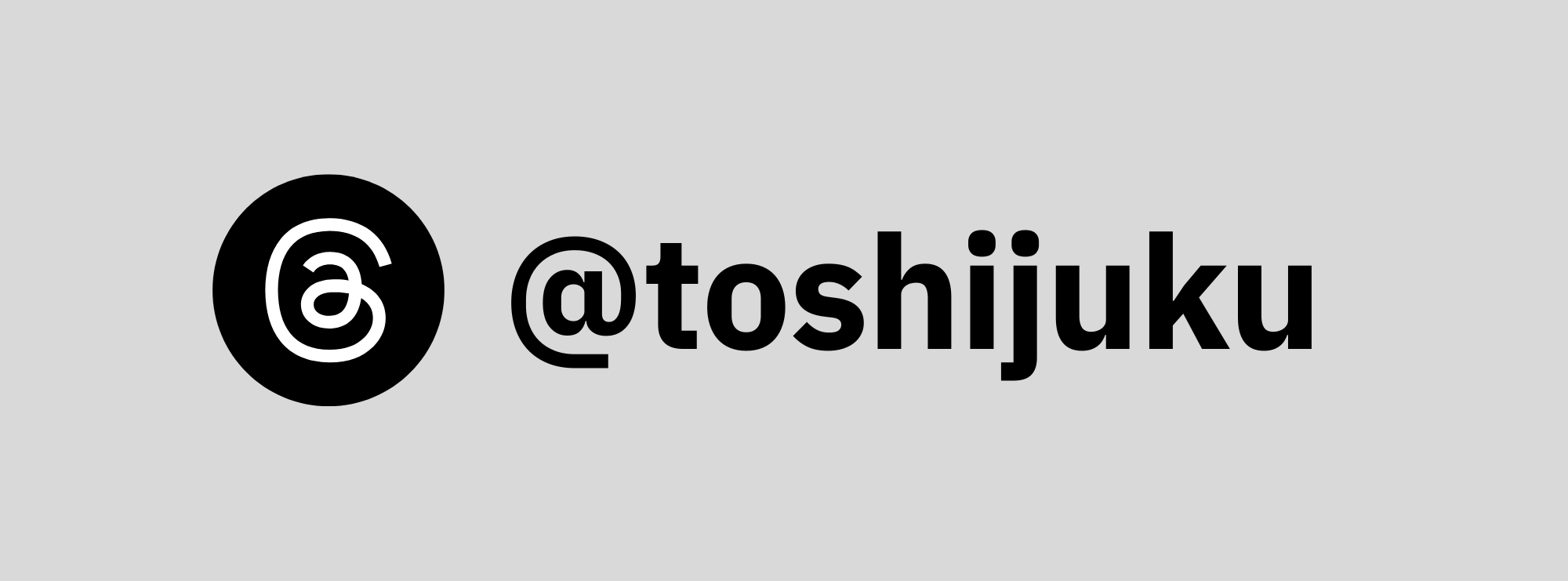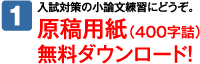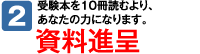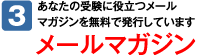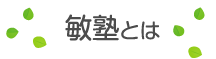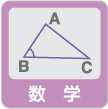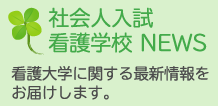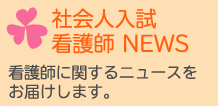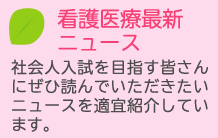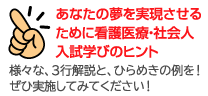- 大垣女子短期大学
- 主な合格実績です。
- 東京都立荏原看護専門学校 松下看護専門学校 愛仁会看護助産専門学校 大阪医療センター附属看護学校 盛岡看護医療大学校

- 藍野大学短期大学地域看護学専攻 滋賀県立看護専門学校 近江八幡市立看護専門学校 済生会看護専門学校 東洋医療専門学校

- 藍野大学短期大学部 埼玉県坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 瀬戸旭看護専門学校 京都府医師会看護専門学校 東京都立荏原看護専門学校

- 安城市医師会安城碧海看護専門学校 製鉄八幡看護専門学校 鹿児島医療福祉専門学校 御殿場看護学校 厚木看護専門学校

- 千葉大学 青森県立保健大学 横浜市病院協会看護専門学校 泉州看護専門学校 埼玉県立高等看護学院
有元利夫(画家)プロフィール・死因:肝臓癌で死去(日本医科大学病院)最後の作品群

有元利夫とは誰か【プロフィールと経歴】
有元利夫(ありもと としお)さんは、1946年に岡山県津山市で四兄弟の末っ子として生まれました。戦後間もない時期で、家族は疎開先での生活を送っていましたが、生後まもなく東京へ戻り、下町の谷中で幼少期を過ごしています。
東京藝術大学デザイン科で学んだ理由とイタリア旅行
高校卒業後、有元利夫さんは東京藝術大学デザイン科に進学します。絵画科ではなくデザイン科を選んだ理由については、「当時はまだ画家として生きる覚悟が固まっていなかったため」と語られることが多いです。在学中に訪れたイタリア旅行は、有元利夫さんの人生を大きく変える出来事でした。そこで出会ったフレスコ画の静謐さと永遠性に深い感銘を受け、「自分もこのような時間を超える絵を描きたい」と強く思うようになります。
電通デザイナーから画家へ転身した背景
1973年、東京藝術大学を卒業した有元利夫さんは、大手広告代理店の電通にデザイナーとして入社します。しかし、広告の仕事は「目的が明確で、期限がある」世界です。有元さんが求めていたのは、もっと静かで、永遠性を感じさせる表現でした。
安井賞受賞と画壇での評価
1978年、有元利夫さんは「花降る日」で安井賞特別賞を受賞し、画壇から注目される存在になります。さらに1981年には代表作「室内楽」で安井賞を受賞し、若手画家として確固たる地位を築きました。有元利夫さんの作品は、評論家からは「静けさの画家」「祈りの画家」と呼ばれました。
有元利夫の作風と特徴【フレスコ画×仏画×岩絵具】
有元利夫さんの作風を語るうえで欠かせないのが、学生時代に訪れたイタリアで出会ったフレスコ画です。特にジョットやピエロ・デラ・フランチェスカの作品は、彼に決定的な影響を与えました。
日本の仏画との共通点に気づいた転換点
イタリアのフレスコ画を研究する中で、有元利夫さんは日本の仏画との共通点に気づきます。どちらも写実より象徴性を重視し、人物は正面性を持ち、背景は簡素で余白が多いという特徴があります。東西の美術の共通性を見出し、それを自らの作品に融合させることで、独自の世界観を築き上げていきます。
岩絵具・金泥・箔を使った独自技法
有元利夫さんの作品は油彩でありながら、岩絵具・金泥・箔といった日本画の素材を積極的に取り入れています。画面には細かな凹凸があり、光の当たり方によって表情が変わります。これにより、作品は「時間の経過」や「永遠性」を感じさせる独特の深みを持つようになります。
静謐で象徴的な世界観の魅力
有元利夫さんの作品は、どれも静けさに満ちています。人物はほとんど動きを見せず、背景は簡素で、余白が大きく取られています。また、有元さんは音楽を愛しており、作品にはリズムや間が意識されています。
有元利夫の死因は肝臓癌【日本医科大学病院で死去】
有元利夫さんが肝臓癌と診断された正確な時期は公表されていませんが、1980年代前半には体調不良が続き、制作量が徐々に減っていったことが記録されています。当時の医療技術では早期発見が難しく、気づいた時には病状が進行していた可能性が高いと考えられています。作品の変化からも、病と向き合いながら制作を続けていたことが読み取れます。
闘病中の生活と制作スタイルの変化
病状が進むにつれ、大作を描く体力は次第に失われていきました。しかし、有元利夫さんは創作への意欲を失わず、小作品・版画・素描を中心に制作を続けています。晩年の作品は、色彩が抑えられ、構図はより簡素になり、人物の象徴性がさらに強まります。これは体力の問題だけでなく、病と向き合う中で精神性が研ぎ澄まされていった結果とも言えます。
死去した場所と最期の様子
1985年2月24日、有元利夫さんは日本医科大学病院で息を引き取りました。38歳という若さでの死は、家族や友人、そして美術界に大きな衝撃を与えました。妻と息子(長男)に見守られながらの最期であったとされ、家族の証言からは「最後まで創作への意欲を持ち続けていた」姿が語られています。
病と向き合いながら描いた「最後の作品群」
1983年頃から亡くなる1985年までの約2年間は、有元利夫さんにとって特別な時期でした。体調が悪化し、制作できる時間が限られていく中で、作品のテーマはより深く、より精神性の高いものへと変化していきます。この時期の作品には、「祈り」「永遠」「沈黙」「存在の気配」といったテーマが強く表れています。また、晩年の作品には「時間が止まったような感覚」があり、鑑賞者に深い余韻を残します。
色彩・構図・象徴性の変化
有元利夫さんの晩年の作品では、色彩がより抑制され、落ち着いたトーンが多くなります。初期の作品に見られる鮮やかな色彩は影を潜め、代わりに金泥や箔の使い方が洗練され、画面に静かな輝きを与えています。象徴性も強まり、人物の表情や姿勢はほとんど変化がありませんが、その静けさの中に「内なる緊張」や「祈りの気配」が宿っています。
未完の作品が語るもの
晩年には、完成に至らなかった作品もいくつか残されています。未完の作品には、筆の途中で止まった線や、塗りかけの色面がそのまま残っており、有元利夫さんが最後まで創作への意欲を持ち続けていたことが伝わってきます。
有元利夫の家族【妻・有元容子と長男】
有元利夫さんは四兄弟の末っ子として生まれ、兄たちに囲まれた賑やかな家庭で育ちました。幼い頃から絵を描くことが好きで、家族の姿や身の回りの風景をよくスケッチしていたと言われています。
妻・有元容子(日本画家・陶芸家)との関係
有元利夫さんの妻である有元容子さんは、日本画家・陶芸家として活動しており、芸術的な感性を共有する存在でした。二人は東京藝術大学で出会い、1972年に結婚しています。有元利夫さんの死後も、有元容子さんは作品の保存や展覧会の開催に尽力し、夫の芸術を後世に伝える役割を果たしています。
家族が語る晩年のエピソード
NHK「日曜美術館」などの番組では、家族が語る晩年のエピソードが紹介されています。妻の容子さんや息子(長男)は、有元さんが病と向き合いながらも、最後まで創作への意欲を失わなかったことを語っています。体調が悪い日でも、少しでも筆を持てる時間があれば制作に向かい、作品に向き合う姿勢を崩さなかったと言われています。家族にとって、その姿は「生きることと描くことが一体化していた」ように見えたそうです。
宮本輝との関係【文学と絵画の共鳴】
作家の宮本輝さんと有元利夫さんは、直接の交友関係があったわけではありません。しかし、宮本輝さんの文春文庫の多くで、有元利夫さんの絵が表紙に採用されています
まとめ【有元利夫の生涯と作品の核心】
有元利夫さんは、フレスコ画と仏画の精神性を融合させ、独自の静謐な世界を築いた画家です。作品には、時間を超えるような静けさと永遠性が宿っています。
病と向き合いながら到達した境地
晩年の作品には、病と向き合いながらも創作を続けた有元利夫さんの強い意志が表れています。限られた時間の中で描かれた作品は、精神性が高く、深い余韻を残します。
短い生涯が残した深い余韻
38年という短い生涯でしたが、有元利夫さんが残した作品は今も多くの人々に愛され続けています。静けさの中に宿る強い存在感は、これからも長く語り継がれていくでしょう。
【参考資料】
・東文研アーカイブ
・NHK「日曜美術館」
・弥生画廊資料
・美術関連書籍・画集
●自分らしい人生を歩みたい ●周囲は「合格できるはずない」と言うけど、合格して見返したい ●人のために働きたい●久々の勉強だけど挑戦したい
●家族を安心させたい ●年齢的に不安はあるけど頑張りたい ●看護医療の仕事が好きだ。もっと極めたい●何度受験しても不合格だった。今度こそリベンジしたい
●社会人の看護医療系受験を専門にずっと教えてきたプロから指導を受けたい ●看護学校を中退した過去があるけど、その学校を再受験してやり直したい ●新しいことにチャレンジしたい ●とにかく絶対合格したい ●学生時代、勉強は今までサボってきた。でも、やるしかない。逃げたくない ●経済的に自立して離婚したい ●今の会社を辞めたい ●自身の闘病経験や障害を活かしたい ●外国籍だけど看護師になりたい ●緊張すると実力が出せない。そういう自分を変えたい ●応援してくれる家族や周囲の期待に応えたい ●この受験を自分の成長の糧にしたい