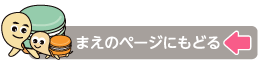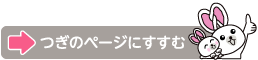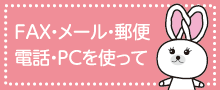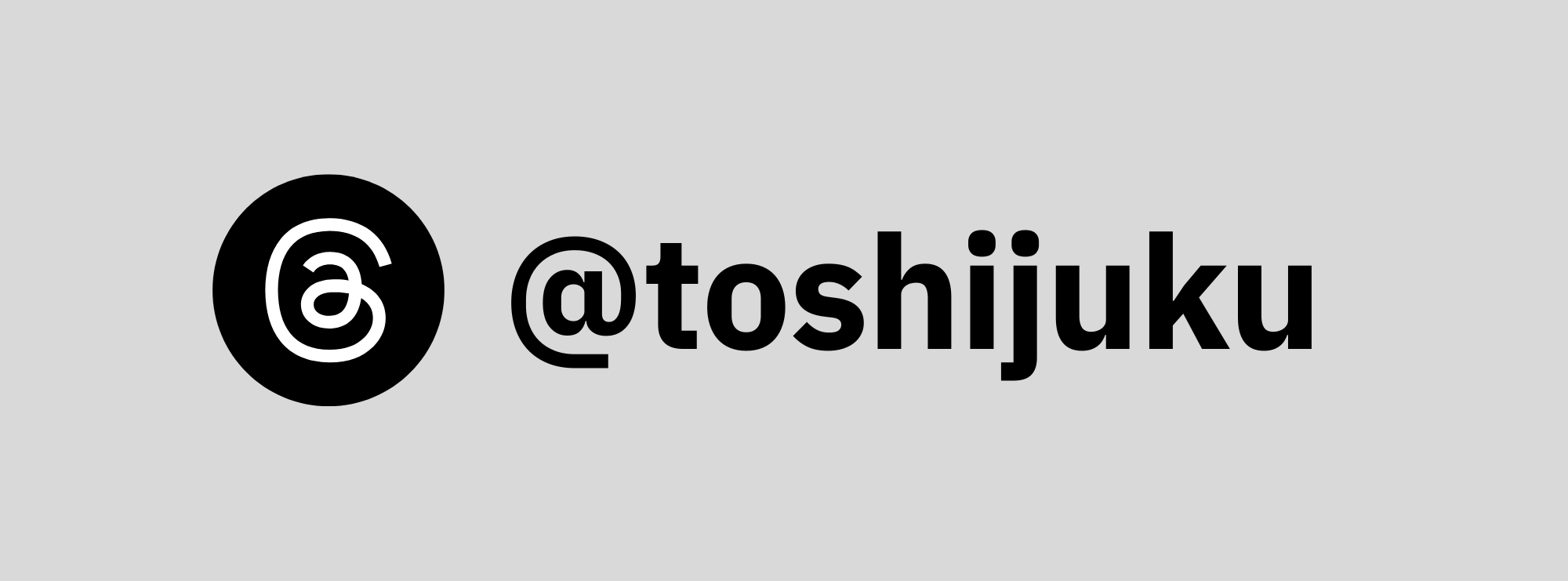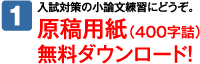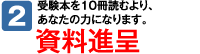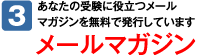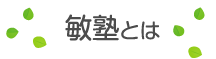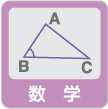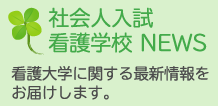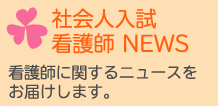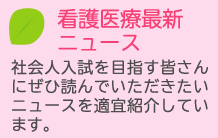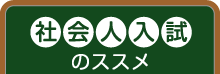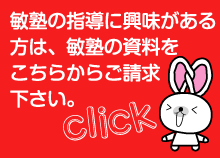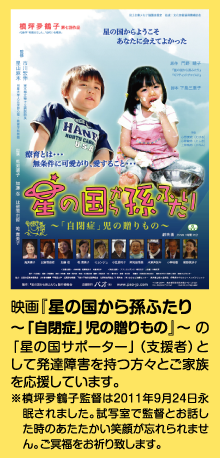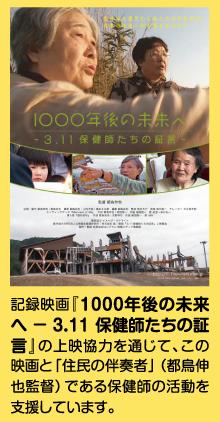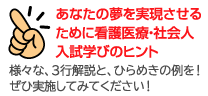- 大垣女子短期大学
- 主な合格実績です。
- 病院採用試験内定 東京都青梅看護専門学校 京都大学 専門学校高崎福祉医療カレッジ 看護協会認定看護管理者サードレベル

- 東京衛生学園看護学科二年課程 (通信制) 大阪保健福祉専門学校 マロニエ医療福祉専門学校 大阪市立大学(保健師選抜) 社会福祉法人健祥会学園

- 日本聴能言語福祉学院 津島市立看護専門学校 愛知県立総合看護専門学校 藤華医療専門学校(理学療法士学科) 日本文理大学医療専門学校(放射線技師学科)

- 新潟看護医療専門学校 白鳳短期大学 児湯准看護学校 福岡国際医療福祉大学 聖マリアンナ医科大学看護専門学校

- 湘南医療大学公衆衛生看護学専攻科 熊本看護専門学校 御殿場看護学校 東京都立青梅看護専門学校 聖路加看護大学
人生会議(ACP)とは:看護師が名付け親だった?医療と対話の新しいかたち

人生会議とは?──ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の日本版
「人生会議」とは、将来の医療やケアについて、本人が元気なうちに家族や医療者と話し合い、意思を共有しておく取り組みです。これは、専門的にはACP(アドバンス・ケア・プランニング)と呼ばれ、厚生労働省が2018年から普及を進めています。
目的は、「もしものとき」に備えて、自分らしい生き方や医療の選択を事前に考え、周囲と共有しておくこと。意思表示ができなくなったときでも、本人の価値観に沿った医療が提供されるようにするための仕組みです。
名付け親は看護師──公式サイトで語られた現場の声
「人生会議」という言葉は、厚生労働省が2018年に実施したACPの愛称公募で選ばれたものです。応募総数1,073件の中から選ばれたこの名称を提案したのは、静岡県浜松市・聖隷浜松病院の集中治療室で働く看護師・須藤麻友さん。
この事実は、聖隷浜松病院の公式ブログにて紹介されています。須藤さんは、重篤な患者さんと日々向き合う中で、「本人の意思がわからないまま医療を進めること」に葛藤を感じていたと語っています。
そこから、「元気なうちに、人生の大切な選択を"会議"のように話し合ってほしい」という願いを込めて、「人生会議」という言葉を提案したのです。
看護師の役割──人生会議を支える"気づき"と"つなぎ"
- 日常の変化に気づく力:患者さんの小さな変化に敏感で、ACPのきっかけをつくる存在です。
- 医師と家族の橋渡し:本人の気持ちを医療チームに伝えることで、より納得のいく医療選択を支援します。
- 継続的な支援と記録:人生会議は一度きりではなく、繰り返し話し合うもの。看護師はその過程を記録し、必要に応じて再対話を促します。
国の取り組み──「人生会議の日」と地域の広がり
厚生労働省は、毎年11月30日を「人生会議の日」と定めています。これは「いい看取り・看取られ(11=いい、30=みと)」という語呂から来ており、命の終わりに向き合うことを前向きに考えるきっかけの日とされています。
香川県や大阪府など、自治体単位での普及啓発イベントも活発です。たとえば香川県では、落語家によるオリジナル落語や専門家の講演など、親しみやすい形で人生会議の大切さが伝えられています。
まとめ──人生会議は「自分らしく生きる」ための準備
人生会議は、「死を語る場」ではなく、「生き方を共有する場」。名付け親が看護師だったという事実は、医療の現場から生まれた本当の願いを物語っています。
静かな夜に、「自分らしさ」について話してみる時間。それが、人生会議の第一歩かもしれません。
●自分らしい人生を歩みたい ●周囲は「合格できるはずない」と言うけど、合格して見返したい ●人のために働きたい●久々の勉強だけど挑戦したい
●家族を安心させたい ●年齢的に不安はあるけど頑張りたい ●看護医療の仕事が好きだ。もっと極めたい●何度受験しても不合格だった。今度こそリベンジしたい
●社会人の看護医療系受験を専門にずっと教えてきたプロから指導を受けたい ●看護学校を中退した過去があるけど、その学校を再受験してやり直したい ●新しいことにチャレンジしたい ●とにかく絶対合格したい ●学生時代、勉強は今までサボってきた。でも、やるしかない。逃げたくない ●経済的に自立して離婚したい ●今の会社を辞めたい ●自身の闘病経験や障害を活かしたい ●外国籍だけど看護師になりたい ●緊張すると実力が出せない。そういう自分を変えたい ●応援してくれる家族や周囲の期待に応えたい ●この受験を自分の成長の糧にしたい