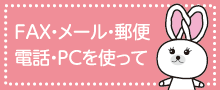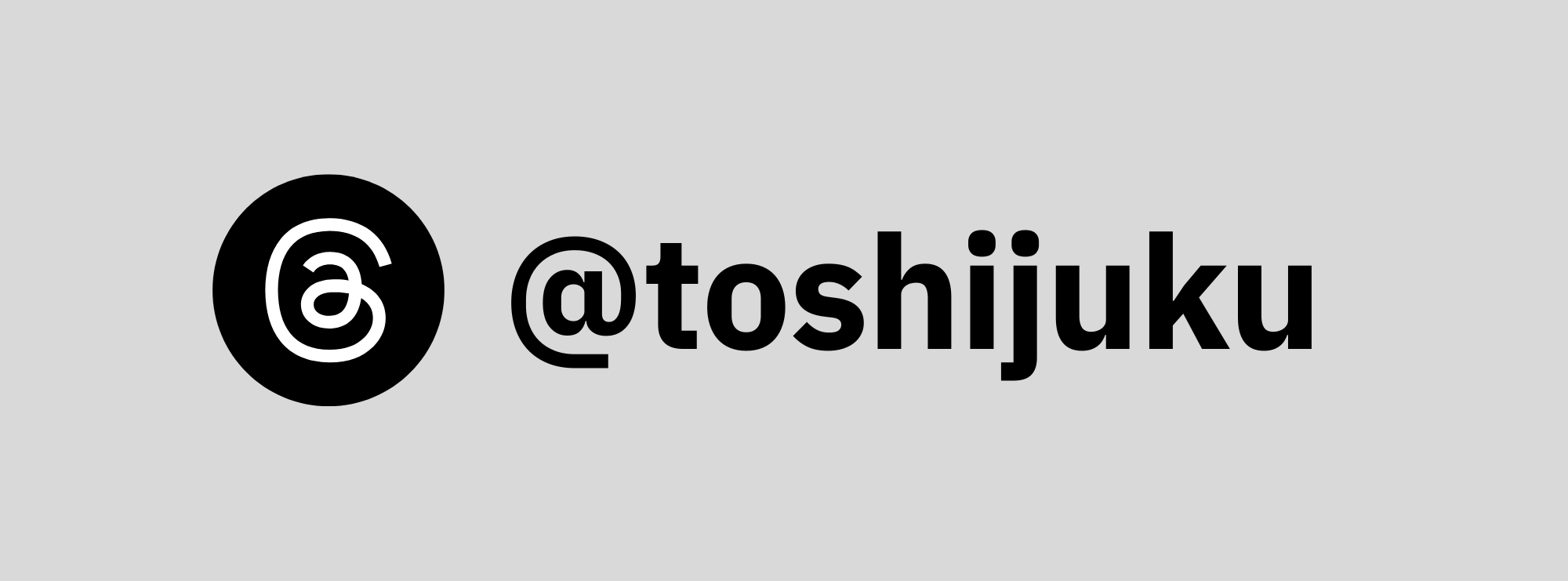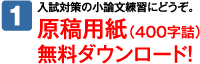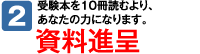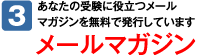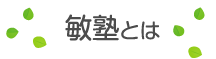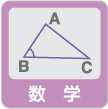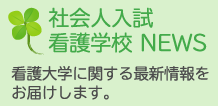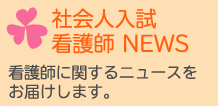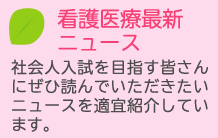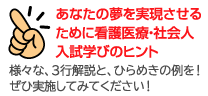- 大垣女子短期大学
- 主な合格実績です。
- 所沢准看護学院 独協医科大学附属看護専門学校 鳥取県立鳥取看護専門学校 三重大学大学院医学系研究科 美原看護専門学校

- 都城羊香看護専門学校 宮城大学 佐賀大学看護学科 水戸医師会看護学院 西埼玉中央病院附属看護学校

- 富山大学医学部看護学科 浦田医師会立看護高等専修学校 名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 大阪府立大学 佐山准看護学校

- 滋賀県済生会看護専門学校 滋賀県立大学 慈恵看護専門学校 静岡県立大学短期大学部 山形厚生看護学校

- 横浜リハビリテーション専門学校 洛和会京都看護学校 立命館大学 渋谷区医師会附属看護高等専修学校 島根県立看護短期大学部 厚木看護専門学校
『アトピッ子』斎藤範夫
「うちの子にストロイドは使わないでください」
と母親は冷めた口調で言った。
「しかし、お母様」
と医者は小さな抵抗を試みたが、彼の弱々しい言い方では、どんなに物わかりのいい人間だって説得されることはなかったろう。しかも、こういった事態に医者は慣れっこになっているらしかった。法律的にも自分らの権限のなさをすっかり自覚しているらしく、すぐに母への説得を放棄してしまうのだった。
僕もほとんど観念していた。今日はこのまま家に引き戻され、母が新しく仕入れてきた酵素剤入りのクリームを全身に塗られ、痒みと痛みに耐えながらフトンに潜り込むことになるのだろう。(略)
⠀
しかし僕をより苛立たせたのは、傍観している医者の中途半端な態度なのだった。母のステロイドに対する誤解を説き伏せ、この場を収拾するのが彼の仕事のはずなのに、あろうことか僕を売ろうとするのだ。
(『アトピッ子』斎藤範夫/2004年3月6日初版/株式会社健友館)
※母、医者、そして、この「僕」...皆の思いがあるのでしょうけど、誰もが納得していないようです(敏塾)
●今のままの自分でいたくない ●ずっと前から看護師になりたかった ●万一のときも子供たちを守るために資格がほしい ●生活・収入・将来を安定させたい
●自分らしい人生を歩みたい ●周囲は「合格できるはずない」と言うけど、合格して見返したい ●人のために働きたい●久々の勉強だけど挑戦したい
●家族を安心させたい ●年齢的に不安はあるけど頑張りたい ●看護医療の仕事が好きだ。もっと極めたい●何度受験しても不合格だった。今度こそリベンジしたい
●社会人の看護医療系受験を専門にずっと教えてきたプロから指導を受けたい ●看護学校を中退した過去があるけど、その学校を再受験してやり直したい ●新しいことにチャレンジしたい ●とにかく絶対合格したい ●学生時代、勉強は今までサボってきた。でも、やるしかない。逃げたくない ●経済的に自立して離婚したい ●今の会社を辞めたい ●自身の闘病経験や障害を活かしたい ●外国籍だけど看護師になりたい ●緊張すると実力が出せない。そういう自分を変えたい ●応援してくれる家族や周囲の期待に応えたい ●この受験を自分の成長の糧にしたい
●自分らしい人生を歩みたい ●周囲は「合格できるはずない」と言うけど、合格して見返したい ●人のために働きたい●久々の勉強だけど挑戦したい
●家族を安心させたい ●年齢的に不安はあるけど頑張りたい ●看護医療の仕事が好きだ。もっと極めたい●何度受験しても不合格だった。今度こそリベンジしたい
●社会人の看護医療系受験を専門にずっと教えてきたプロから指導を受けたい ●看護学校を中退した過去があるけど、その学校を再受験してやり直したい ●新しいことにチャレンジしたい ●とにかく絶対合格したい ●学生時代、勉強は今までサボってきた。でも、やるしかない。逃げたくない ●経済的に自立して離婚したい ●今の会社を辞めたい ●自身の闘病経験や障害を活かしたい ●外国籍だけど看護師になりたい ●緊張すると実力が出せない。そういう自分を変えたい ●応援してくれる家族や周囲の期待に応えたい ●この受験を自分の成長の糧にしたい