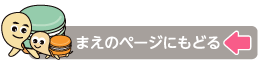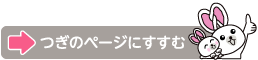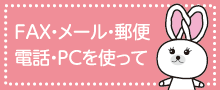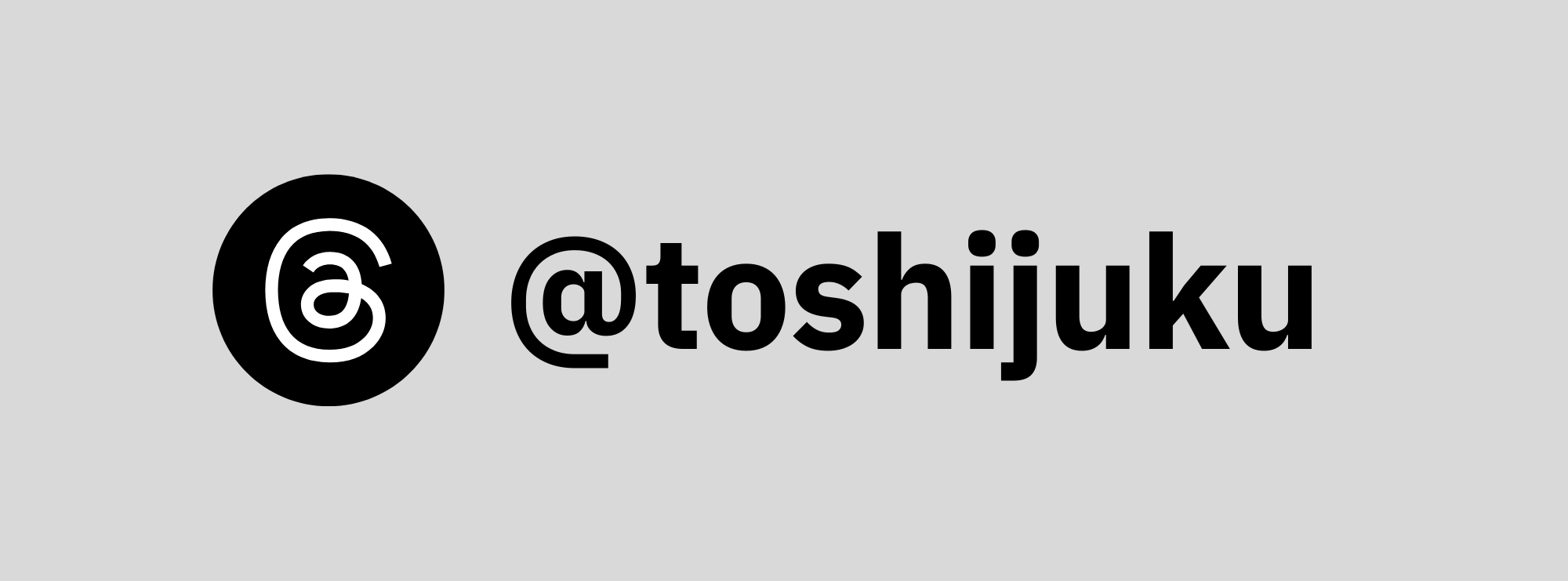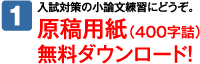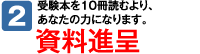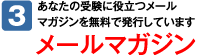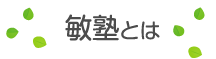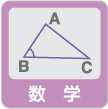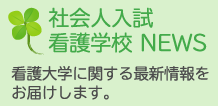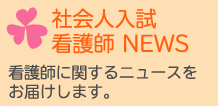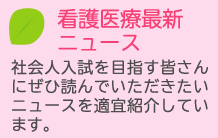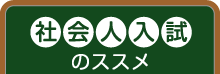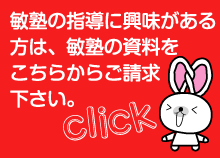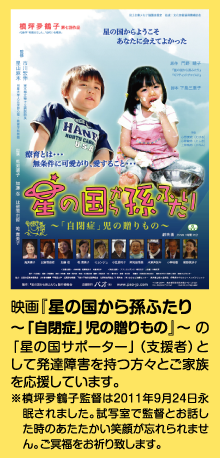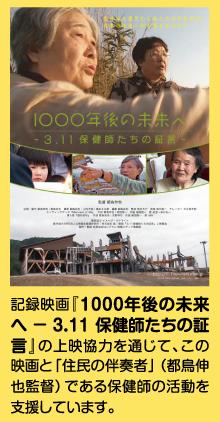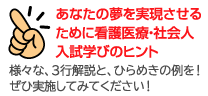- 大垣女子短期大学
- 主な合格実績です。
- 東京医科大学看護学部 八王子市立看護専門学校 大阪府病院協会看護専門学校 大阪医療センター附属看護学校

- 神戸市医師会看護専門学校 尾道市医師会看護専門学校 熊本駅前リハビリテーション学院看護学科 川崎市立看護短期大学

- 聖バルナバ助産師学院 東京都立府中看護専門学校 湘南看護専門学校聖灯看護専門学校 川口市立看護専門学校

- 甲府看護専門学校 学校法人湘央学園浦添看護学校 東京女子医大看護学校 墨田看護専門学校 横浜中央看護専門学校

- 行岡医学技術専門学校看護第1学科 大阪行岡医療専門学校鍼灸科 首都大学東京大学院人間健康科学研究科(博士前期課程) たかさき・ナイチンゲール学院
大関増裕とは:幕末期の黒羽藩主。縁戚にトレインドナース大関和
大関増裕(おおぜき ますひろ、1838年~1868年)は、江戸時代末期の下野国黒羽藩第15代藩主です。遠江国横須賀藩主・西尾忠宝の三男として生まれ、文久元年(1861年)に大関家の養子となり、家督を継ぎました。大関増裕は、蘭学を学び、オランダ語や英語にも精通、西洋の学問や文化に深い関心を持ち、洋式兵術も習得していました。
大関増裕は、幕末の動乱期に幕府の重要な役職を歴任されました。文久2年(1862年)に陸軍奉行、慶応元年(1865年)に新設された海軍奉行、そして慶応3年(1867年)には若年寄に就任し、軍備の強化に尽力しました。外様大名であるにもかかわらず異例の抜擢を受けたのは、危機的な状況下で幕府がその能力を高く評価したためと考えられています。
藩政においては、文久3年(1863年)に全権を委ねられ、改革を断行されました。財政再建のために勧農方を設立したり、西洋式の兵制を導入したりしました。また、藩校「作新館」(勝海舟が命名したとされています)を創設するなど、富国強兵と人材育成に力を注ぎました。
大関増裕の縁戚には、トレインドナースとして知られる大関和がいます。大関和の父・大関弾右衛門は大関増裕の縁戚にあたり、大関和は幼い頃、大関増裕から外国語の書物を見せられ、異国の言葉の存在を知ったそうです。
大関増裕は慶応3年12月9日、狩猟中の猟銃暴発事故により、31歳という若さで急逝されました。死因については諸説ありますが、戊辰戦争が始まる直前の彼の死は、黒羽藩の運命に大きな影響を与えたと推測されています。
参考:明治のナイチンゲール大関和物語(田中ひかる)、デジタル版 日本人名大辞典+Plus 、Wikipedia、日本の歴史ガイド~日本のお城 城跡 史跡 幕末、大田原市立図書館、コトバンク
●自分らしい人生を歩みたい ●周囲は「合格できるはずない」と言うけど、合格して見返したい ●人のために働きたい●久々の勉強だけど挑戦したい
●家族を安心させたい ●年齢的に不安はあるけど頑張りたい ●看護医療の仕事が好きだ。もっと極めたい●何度受験しても不合格だった。今度こそリベンジしたい
●社会人の看護医療系受験を専門にずっと教えてきたプロから指導を受けたい ●看護学校を中退した過去があるけど、その学校を再受験してやり直したい ●新しいことにチャレンジしたい ●とにかく絶対合格したい ●学生時代、勉強は今までサボってきた。でも、やるしかない。逃げたくない ●経済的に自立して離婚したい ●今の会社を辞めたい ●自身の闘病経験や障害を活かしたい ●外国籍だけど看護師になりたい ●緊張すると実力が出せない。そういう自分を変えたい ●応援してくれる家族や周囲の期待に応えたい ●この受験を自分の成長の糧にしたい