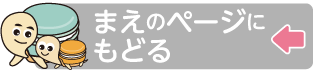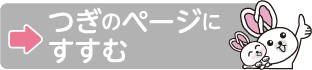【新プロジェクトX】ドクターヘリ新生児搬送とは(熊本市民病院・茨聡と鹿児島市立病院・平川英司両医師)熊本地震


ドクターヘリとは何か?
ドクターヘリは、医師や看護師が同乗し、現場に急行してその場で治療を開始できる救急医療専用のヘリコプターです。正式には「救急医療用ヘリコプター」と呼ばれ、1999年に日本で初めて導入されました。
新生児搬送とは?赤ちゃんを運ぶ──命をつなぐ医療の最前線
新生児搬送は、出生直後に集中治療を必要とする赤ちゃんを、NICU(新生児集中治療室)を備えた医療機関へ安全に移送する医療行為です。未熟児や呼吸循環の補助を要する新生児では、保育器・酸素供給・体温管理などの支援を搬送中も継続できる体制が不可欠です。
熊本地震での新生児搬送──熊本市民病院からの緊急対応
2016年の熊本地震では、熊本市民病院が被災し、NICUの赤ちゃんを県外含む複数施設へ分散搬送する必要が生じました。院内機能の制約下で、赤ちゃんの安全を優先した迅速な搬送計画が立てられました。
鹿児島市立病院とは?──地域医療と周産期医療の中核
鹿児島市立病院は鹿児島市が設置する公立総合病院で、地域医療支援・災害対応・周産期医療を担う拠点です。災害時の広域支援にも関与し、近隣県の緊急搬送に協力する体制を備えています。
ドクターヘリによる新生児搬送体制の整備
同院が運用するドクターヘリは、新生児搬送に必要な保育器等の機材を搭載してNICUに近いレベルのケアを機上で継続できることが特徴です。地上交通が遮断される災害時でも、屋上ヘリポート発着と連携により迅速な搬送が可能です。
茨聡医師と平川英司医師、看護師、助産師も奔走──新生児搬送・新生児内科
茨聡(いばら さとし)医師は、鹿児島市立病院で周産期・新生児医療の推進役として、新生児搬送や空路搬送体制の整備に尽力してきた医師です。地方でも都市部と同等の医療を目指す信念が、実地の搬送体制強化へつながりました。
平川英司(ひらかわ えいじ)医師は、熊本地震時にDMAT等の災害医療チームと情報共有・連携し、体重1000g未満の赤ちゃんを含む搬送を短時間で連続実施。報道では18時間・11フライト、2日間で10人(母親含む)を県境を越えて搬送した記録が示されています。
※番組では、茨聡医師、吉原秀明医師、平川英司医師、井上武医師、村本順一医師、稲田敏医師、岩本渚助産師、石崎紗矢香看護師、山口万里子看護師ら多くの医療従事者が登場します。
医療格差と地域連携の要点
災害下では「都市部なら助かる命」を地方でも守るため、搬送手段・人材・機材の事前整備と、広域連携が鍵となります。鹿児島のドクターヘリが赤ちゃん搬送を担うことで、他のヘリや医療資源を別患者へ振り向ける分散最適化が実現しました。
参考資料
- NHK「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜 ドクターヘリ赤ちゃんの砦を守れ 熊本地震18時間の救出劇」番組案内(語り・人物言及あり)
- 熊本日日新聞「鹿児島のドクターヘリ 赤ちゃん搬送に尽力」熊本市民病院編(2017年4月11日)
- 鹿児島市立病院資料(災害対応・広域支援に関する記述含む)
- メディア記事「平川英司 医師のプロフィール・出演」新プロジェクトX関連(2025年6月14日)
- 熊本日日新聞「県外医師奔走...ヘリでピストン搬送」(2017年4月9日)保育器搭載・DMAT連携の記述