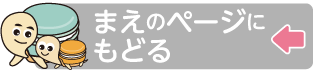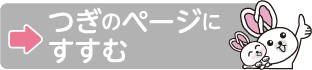心不全パンデミックとは:筒井裕之・下川宏明による警鐘

心不全パンデミックとは、新型コロナウイルスのような感染症ではないものの、心臓のポンプ機能が低下する心不全の患者が社会全体で爆発的に増加している深刻な状況を指す言葉です。日本の心不全治療に携わる専門家たちが、この危機的な状況を広く社会に伝えるために使い始めました。
特に、日本心不全学会の理事長を務めた筒井裕之氏(九州大学大学院教授)が、この言葉を用いて警鐘を鳴らしたことで知られています。
この言葉が生まれた背景には、日本の急速な高齢化があります。心不全は、加齢とともに心臓の機能が衰えることや、高血圧や糖尿病といった生活習慣病が主な原因となるため、高齢化が進む日本では今後も患者が増え続けることが確実視されています。
2015年にEuropean Journal of Heart Failure誌に掲載された、下川宏明氏らの論文「Heart failure as a general pandemic in Asia」は、この危機的状況を裏付ける重要なデータを示しました。論文内では、日本における心不全の疫学データがまとめられ、2005年時点での左心室機能不全を持つ患者数が約97万9千人と推定され、2020年までに5年ごとに約9万人ずつ増加すると予測されていました。これは、心不全患者数がやがてがん患者数を上回るという予測にも繋がり、その深刻さを「パンデミック」という言葉で表現することで、社会全体の関心を喚起する狙いがありました。
心不全は一度発症すると完治が難しく、入退院を繰り返すことで患者のQOL(生活の質)を著しく低下させます。下川氏らの論文でも、2000年代初頭から心不全治療薬の普及により3年後の死亡率や心不全による入院率は改善したものの、再入院率は依然として高いことが課題として指摘されています。
この心不全の増加は、医療費の増大や病床のひっ迫といった医療現場の問題だけでなく、患者本人のQOLや介護の負担増といった社会的な課題も引き起こしています。この現状を食い止めるためには、高血圧や糖尿病の管理といった予防と早期発見、そして患者とその家族を支える社会全体のサポート体制の構築が不可欠です。この「心不全パンデミック」という言葉は、私たち一人ひとりが心不全の予防に意識を向けるきっかけとなる重要なメッセージと言えるでしょう。